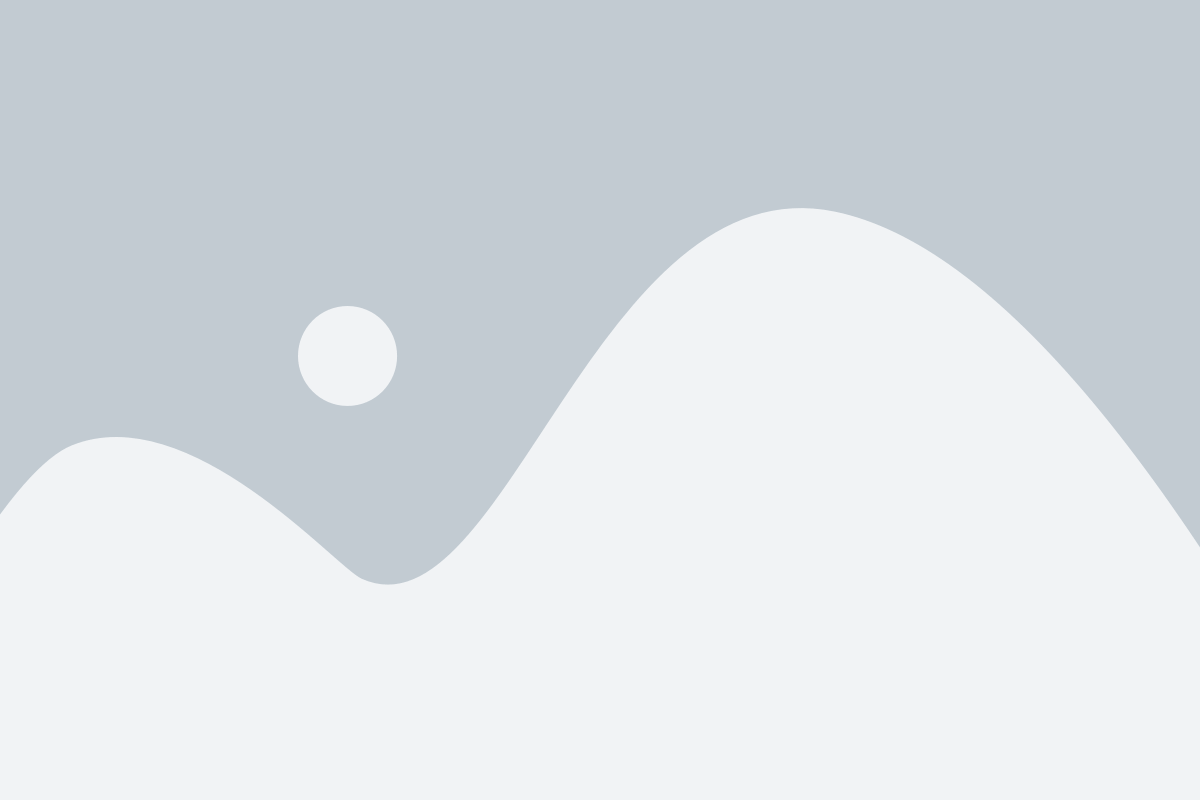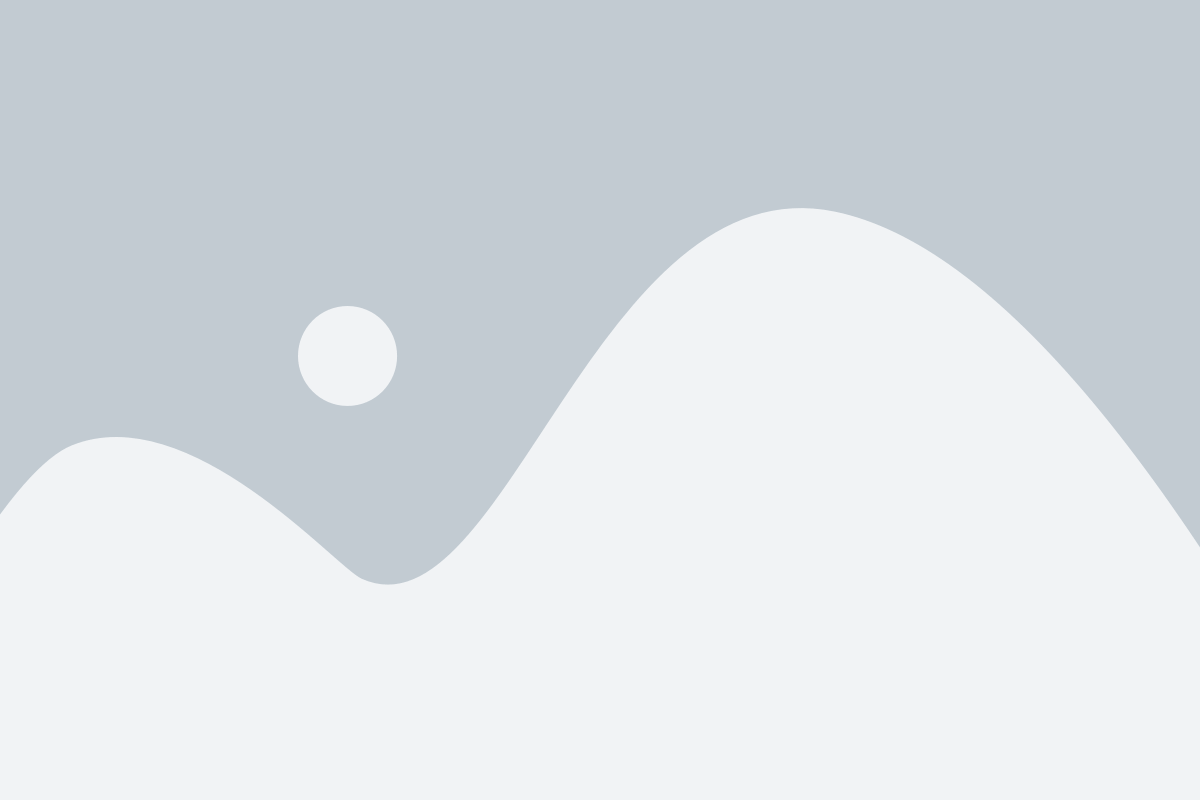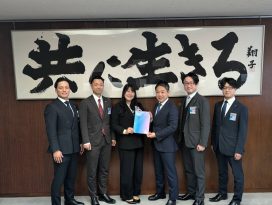立川青年会議所 2026年度スローガン - 覚醒 -Take a step forward-




お知らせ
2026/02/12
お知らせ開催報告青少年委員会
【開催報告】第1053回例会 子どもに伝えるAIと未来
2026/02/07
お知らせ開催報告拡大広報委員会
【開催報告】第49回 塞の神どんど焼き
2026/02/04
お知らせ
【各地会員会議所 賀詞交歓会 訪問最終報告】
2026/01/20
お知らせ
2026/01/20
お知らせ
開催案内
2026/02/13
開催案内Global委員会
【開催案内】第1回Tachikawa Global Play 開催!
2026/02/06
開催案内拡大広報委員会
【開催案内】2026年2月9日オリエンテーション
2026/02/05
拡大広報委員会開催案内
【開催案内】異業種交流会 開催のご案内
2026/02/01
開催案内
【開催案内】第51回衆議院議員総選挙 東京第21区 公示後ネット討論会
2026/01/10
開催案内
【開催案内】第1053回例会 子どもに伝えるAIと未来
開催報告
2026/02/27
開催報告拡大広報委員会
【開催報告】第1回 異業種交流会
2026/02/12
お知らせ開催報告青少年委員会
【開催報告】第1053回例会 子どもに伝えるAIと未来
2026/02/07
お知らせ開催報告拡大広報委員会
【開催報告】第49回 塞の神どんど焼き
2026/02/02
開催報告
【開催報告】衆議院議員総選挙 東京第21区 公示後ネット討論会
2026/01/08
開催報告
【開催報告】第1052回例会 新年賀詞交歓会
理事長 メッセージ

立川青年会議所は1965年に設立され、国際青年会議所の一員として活動を続けてきました。20歳から40歳までの青年が集い、地域社会の課題解決と人材育成に取り組む団体です。これまで青少年育成事業、多文化共生の推進、スポーツや文化を通じた地域連携など、多様な活動を展開し、立川をはじめとする地域の持続的な発展に寄与してまいりました。
2026年度、当会は創立62年目を迎え、「覚醒~私が動けば未来がひらく~」をスローガンに掲げています。これは、一人ひとりが主体者として目を覚まし、自らの意志で行動することで未来を切りひらくという決意を込めたものです。
青年会議所の特徴は、地域貢献団体ではなく、会員自身が成長する「自己修練の場」であることです。事業の企画・運営を通じてリーダーシップを磨き、仲間と議論しながら意思決定を重ねることで、社会人としての力を養います。失敗も成功も経験しながら挑戦を続ける過程そのものが、会員一人ひとりの成長を育みます。そうして得た成長が地域に新たな価値をもたらし、未来を担う世代へと広がっていきます。
立川青年会議所は、一人ひとりが自分らしく輝ける場をつくり出し、その力が繋がり合うことで地域の未来をひらいていくことを目指しています。築かれた歴史や関係を未来へと活かすか否かは、今を生きる私たち次第です。これからも地域と共に歩み、持続可能で包摂的な社会の実現に向けて邁進してまいります。
公益社団法人立川青年会議所
第62代理事長 藤野 直美
理事長 所信
X
🌍 第1回Tachikawa Global Play開催!
テーマは「スポーツのルールは、だれのためにある?」
遊びを通じて異文化理解や考える力を育む、親子向けワークショップです!
📅3/15(日) 10:00-11:30
📍立川市子ども未来センター
👥小1-6と保護者
申込↓↓↓
https://forms.gle/dnaj4aFVPa9Z1KkD6
#立川jc #立川青年会議所
第1053回例会「子どもに伝えるAIと未来」を開催しました👦🏻✨️
世界の先進事例から学ぶAIとの向き合い方。大切な4つの姿勢「よ・う・や・ふ」や、AI時代だからこそ「一次体験」が重要であるというお話は、今後の大きな指針となりました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!#立川jc
1/22〜25、2026年度 京都会議 に参加しました。「TRUE MIND TRUE HOPE」を掲げ、全国の仲間と未来への一歩を踏み出しました。
「幸せ」や「脱炭素」などのフォーラムで得た知見と、7月の立川・関東地区大会への熱い情熱を胸に、地域のために一年間走り抜けます!
#立川JC #立川青年会議所 #京都会議
TikTok
リンク
X
🌍 第1回Tachikawa Global Play開催!
テーマは「スポーツのルールは、だれのためにある?」
遊びを通じて異文化理解や考える力を育む、親子向けワークショップです!
📅3/15(日) 10:00-11:30
📍立川市子ども未来センター
👥小1-6と保護者
申込↓↓↓
https://forms.gle/dnaj4aFVPa9Z1KkD6
#立川jc #立川青年会議所
第1053回例会「子どもに伝えるAIと未来」を開催しました👦🏻✨️
世界の先進事例から学ぶAIとの向き合い方。大切な4つの姿勢「よ・う・や・ふ」や、AI時代だからこそ「一次体験」が重要であるというお話は、今後の大きな指針となりました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!#立川jc
1/22〜25、2026年度 京都会議 に参加しました。「TRUE MIND TRUE HOPE」を掲げ、全国の仲間と未来への一歩を踏み出しました。
「幸せ」や「脱炭素」などのフォーラムで得た知見と、7月の立川・関東地区大会への熱い情熱を胸に、地域のために一年間走り抜けます!
#立川JC #立川青年会議所 #京都会議
TikTok
リンク